合格のコツを華々しく語れるタイプではありません。七回落ち続け、ようやく今回合格しました。けれど、長く戦っている人が次の一歩を踏み出すための“きっかけ”なら、私の記録が役に立つかもしれません。
合格発表の日に思ったこと
スコアの数字より先に、肩の力が抜けました。これまでの六回分の受験票が頭をよぎり、四時半起きの眠たい朝も、昼休みの短い暗唱も、全部つながっていたのだと実感しました。合格は突然やって来たわけではなく、静かに積もったものがある日境界を越えただけでした。
生活の設計図を先に引く
子どもが生まれてから、夜の勉強は壊滅しました。仕事に復帰すると、ソファに沈んだ時点でその日は終わりです。そこで朝型に完全に切り替えました。四時半に起きて出勤前に九十分。昼休みに三十分。合計二時間という枠を、習慣の形に固定しました。時間は増えません。だから質に寄せます。計算は手を動かし、理論は声に出し、復習はその日のうちに閉じる。この三点だけは崩さないと決めました。
独学をいったん降りる決断
費用を言い訳に通信講座を避けてきました。しかし、周囲に一級の先輩も相談相手もいないままでは、方向が合っているかすら分からない。オンデマンド講座を試した瞬間、勉強が平面から立体に変わりました。収益認識から工事進行、引当金、税効果へと論点が“線”でつながる。講義が地図になり、私はようやく現在地を知りました。答案添削では、記述を「定義・趣旨・要件・結論」の骨組みから作る練習を繰り返し、六十秒で口に出せるかを合図に書き始めるようにしました。すると、文章がぶれにくくなり、時間配分の焦りも消えました。
「分かっていない」を可視化する仕組み
長期化のいちばんの原因は、自分の弱点が見えなかったことでした。解ける日もあれば崩れる日もある。これでは七十点の壁は越えられません。そこで、初級の確認テストにまで一度降り、正答でも根拠を説明できなければ即インプットに戻る、という往復を徹底しました。誤答ノートは薄く保ち、原因と再発防止の行動を一行で書く。仕訳は必ず財務諸表のどこに効くのかまで追跡する。数字に意味が宿ると、偶然の正解が減り、再現性が育ちます。
勉強時間が少なくても点に変える工夫
朝の九十分は計算の素振りと弱点講義の短時間視聴、そして直近の過去問一問の答案復元で埋めました。昼の三十分は理論の骨子を声に出すだけに絞ります。週末は総合演習を少なく深く。間違い直しは“なぜ”から入り、“次はどうする”までセットで終える。教材は増やさず、同じ本に余白を書き足していく。気分転換に新しい資料へ逃げないよう、視界をあえて狭くしました。
スコアの停滞期にやめたこと
苦手論点を後回しにする癖を断ちました。低頻度で重い論点は、序盤で捨てるか徹底的に潰すか、どちらかに決めます。中途半端がいちばん時間を奪います。解けたはずの問題を“ノールック合格”扱いにすることもやめました。根拠を言えない正答は黄色信号。合っていても、いったん立ち止まって理由を言語化する。これだけで、当て勘の正解が減っていきました。
本試験の日の過ごし方
難しい設問に遭遇しても、配点は皆同じだと何度も心の中で唱えました。商簿・会計学で理論の貯金を作り、連結と企業結合で取り切る。工簿・原価では差異の原因を言葉にして部分点を拾い続ける。見直しは二十秒で根拠の黒丸を打つだけに限定し、深追いはしない。最後に答案を閉じる瞬間まで、自分で決めた“型”から外れないことだけを意識しました。
合格して見えた景色
独学の限界は根性ではなく、客観視の欠如でした。外部の目が入ると、やるべき順番と答案の型が揃い、迷走コストが消えます。毎日二時間でも、習慣と仕組みがあれば戦える。六回分の不合格は無駄ではなく、七回目のための準備でした。
次の目標と読者へのメッセージ
一級が最終ゴールのつもりでしたが、気づけば簿記そのものに魅せられています。次は簿記論へ。今度こそ一発で通すつもりです。ここまで読んでくださった方へ。長くかかっても大丈夫です。次の一点は、今日の一頁から始まります。朝の机に座り、昨日の自分とだけ比べてみてください。静かな積み重ねは、ある日必ず境界を越えます。
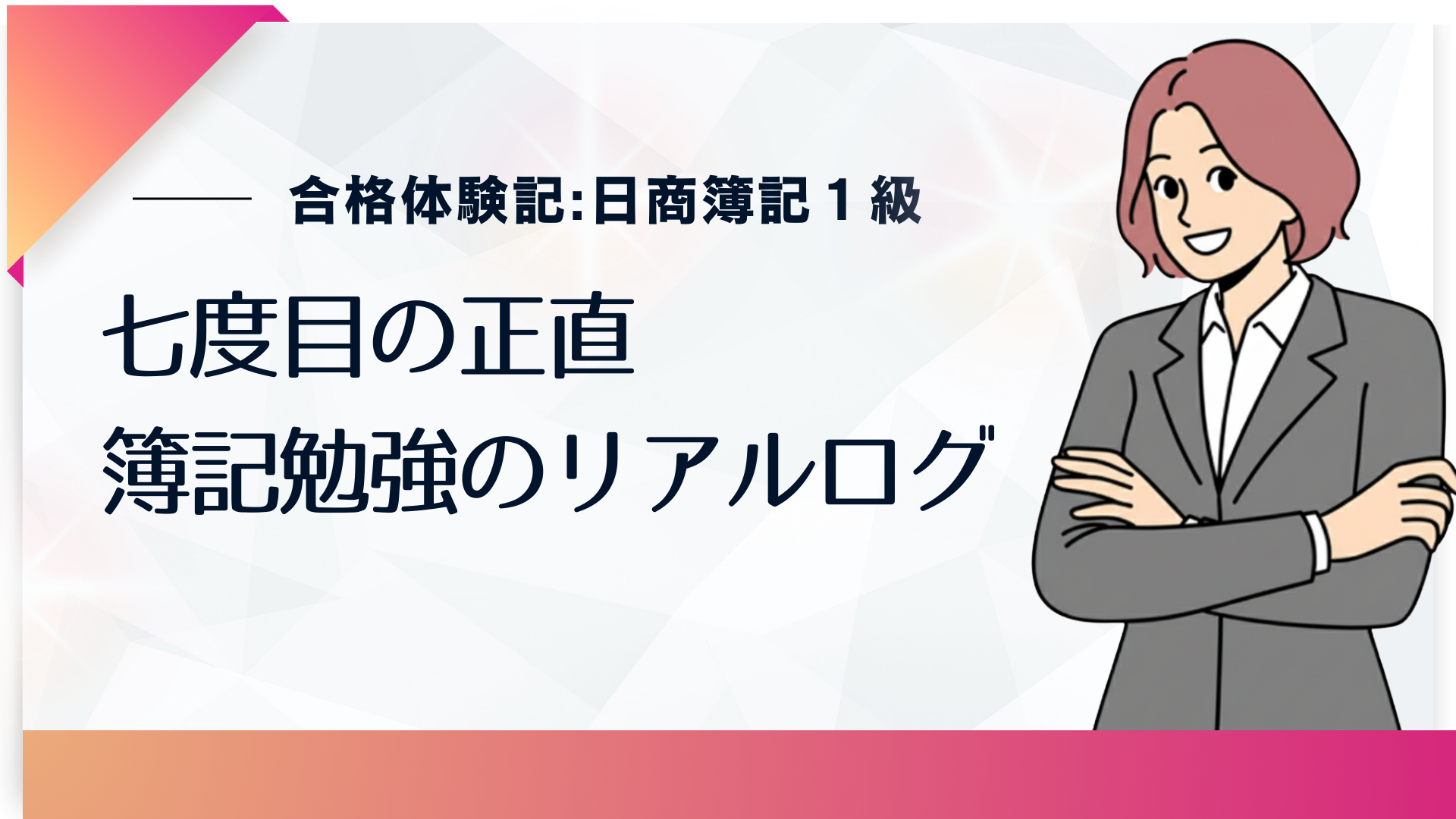
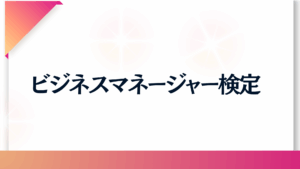
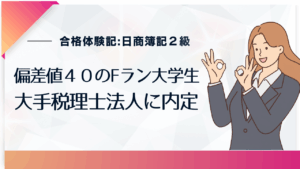
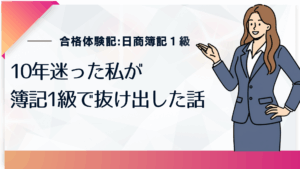
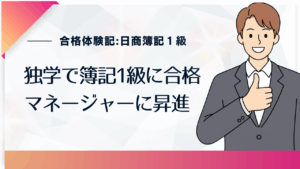
コメント